聖書改ざん陰謀論の真実~エホバの御名を除き去る改ざんは、二,三世紀のクリスチャンによって本当になされたのか?

今回は、ある陰謀論の真相に迫りたいと思います。それは、コロナワクチンやグレートリセット系の陰謀論ではなく、エホバの証人による聖書の改ざんについての陰謀論です。
エホバの証人は、イエスの名よりも「エホバ」のみ名を呼び求めることを最重要なものと見做していますが、その理解の重要な根拠となっている主張の一つが「西暦二,三世紀の背教したクリスチャンたちは,ギリシャ語聖書の写本の写しを作る際にみ名を取り除いた」という陰謀説です。
では、同じような陰謀説を唱える写本研究の専門家はいるのでしょうか?答えは「NO」です。ということは、ものみの塔だけが間違った陰謀説を唱えているのか、あるいはものみの塔だけが正しい真実を唱えているのか、真相はそのどちらかだということです。
今回の記事では、実際にこのような改ざんが2~3世紀にあったのかどうかを、誰にでもわかるような形で解説し、問題の是非を明らかにしていきたいと思います。ぜひ、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
目次
聖書の原本・写本についての基礎知識
本テーマを扱う前に、まずは新約聖書の原本・写本についての基礎的な知識を抑えておきたいと思います。そうした方が、これから説明する内容がより明確に理解しやすくなるからです。
新約聖書の原本は存在しない:今日、新約聖書の原本、つまり聖書筆者たちが書いたオリジナルの巻物は存在しません。この点は旧約聖書においても同様であり、行方がわからなくなっています。時々、この点を例に挙げて聖書の信頼性を批判する人がいるようですが、その批判は、自らをこの分野の素人だと自称しているようなものです。確かに原本はあった方がいいですが、無かったとしても写本がたくさんあれば、オリジナルの文言がかなりの精度でわかるからです。
新約聖書のギリシャ語の写本は五千以上存在する:新約聖書は全てギリシア語で書かれましたが、それらが手書きで書き写された写本(コピー)は、五千以上も存在し、世界中のあらゆる地域から発見されています。この数は、古代文献の中でも圧倒的な多さであり、他の追随を全く許しません。
底本の作成:写本は全て手書きでの写しですから、当然様々な人為的なコピーミスが生じ得ます。ですから、膨大な写本を比較研究し、オリジナルの内容を復元する作業が必要です。このように、現存する多数の写本を比較し、原本に最も近い本文を再構築する学問分野を「本文批評学」と言います。
こうして出来上がった底本に基づき、様々な言語への翻訳が行われます。ものみの塔の発行する「新世界訳」も例外ではなく、キリスト教系の本文批評の専門家たちが作り上げてきた底本に基づき、翻訳が行われてきているのです。
なお、現在の底本は、オリジナルの内容を99.5%以上の精度で再現できていることが確認されており、残る僅かな不明確な部分においても、語順やスペルミスなどの問題に過ぎず、神学的に重要な部分においては原本の意味が十分に保持されていると評価されています。
このように、新約聖書の信頼性は十分に評価されているわけですが、なぜものみの塔は「2~3世紀の背教したクリスチャンたちが、エホバのみ名を取り除いた」という聖書の信頼性を覆すような陰謀説を唱えているのでしょうか?
※聖書の原本や写本についての更なる情報は、こちらの記事をご覧ください。「写本の信頼性―旧新約聖書の原典は正確に書き写されてきたのか?」(TRUE ARK)
ものみの塔は、なぜエホバの御名を取り除く改ざんがあったと主張しているのか?
組織の説明
まずは、この点について、組織がどんなことを述べているのか、出版物の文章から確認しましょう。
「神のみ名と『新約聖書』
ヘブライ語聖書つまり「旧約聖書」の中で,神のみ名は揺るぎない位置を占めています。ユダヤ人はやがてみ名を発音しなくなりましたが,その宗教信念ゆえに,聖書の古い写本を作る際,それを除くことはしませんでした。ですから,ヘブライ語聖書には,神のみ名が他のどの名よりも多く記されています。クリスチャン・ギリシャ語聖書つまり「新約聖書」の場合は事情が異なっています。啓示の書(聖書巻末の書)の写本には,神のみ名が「ヤハ」という省略形で(「ハレルヤ」という語に含まれて)出ています。しかしそれを別にすれば,聖書のマタイから啓示までの書の古代ギリシャ語写本で今日わたしたちが手にしているものの中に,神のみ名をすべての箇所に含んでいるものはありません。それは,み名がそこにあるべきではないという意味でしょうか。イエスの追随者たちが神のみ名の重要性を正しく認識しており,神のみ名が神聖なものとされるよう祈り求めることをイエスがわたしたちに教えた事実からすると,そのようなことは考えられません。では,何が起きたのでしょうか。
それを理解するには,今日わたしたちが手にしているクリスチャン・ギリシャ語聖書の写本は原本ではないことを覚えておかなければなりません。・・・
今日,クリスチャン・ギリシャ語聖書の写本が幾千も存在していますが,その大半は,西暦4世紀以降に作られたものです。これは次の可能性を示唆しています。つまり,西暦4世紀より前にクリスチャン・ギリシャ語聖書の本文に何かが生じ,神のみ名が省かれるようになったのではないだろうかということです。事実は,何かが生じたことを裏付けています。」『神のみ名は永久に存続する』23~24ページ
み名に対する反対
・・・西暦二,三世紀の背教したクリスチャンたちは,ギリシャ語聖書の写本の写しを作る際にみ名を取り除き,聖書の翻訳を行なった時にもみ名を省いてしまいました。・・・」『神のみ名は永久に存続する』27ページ
ここでは、「西暦二,三世紀の背教したクリスチャンたちは,ギリシャ語聖書の写本の写しを作る際にみ名を取り除き,聖書の翻訳を行なった時にもみ名を省いてしまいました。」とあり、御名を除く改ざんがあったことが、あたかも事実であるかのように述べられています。
まず、ものみの塔自身が主張している内容からもはっきりとわかることは、5千を超すギリシア語写本の中には、「エホバのみ名」つまり、神の固有名を表す四つの文字「テトラグラマトン」が一つも出てきません。
そしてこの事実は、エホバの証人にとっては極めて不思議で違和感を覚える問題です。なぜならその事実は、「エホバのみ名の重要性」についての彼らの聖書理解と全く合わないからです。「イエスがわたしたちに教えた事実からすると,そのようなことは考えられません」と先に引用した文章の中でも言っている通りです。
エホバの証人にとっては、イエスの名よりも「エホバの名」の方が重要であり、その名を呼び求めることは彼らにとって最重要な使命です。だからこそ「エホバの証人」という名称まで採択しているのです。ですから彼らにとっては、紀元一世紀の聖書時代のクリスチャンも、同じような基準と熱意をもって「エホバのみ名」を呼び求めていたはずであり、ギリシャ語の原本にもエホバのみ名があったはずなのです。
逆に、もしも一世紀のクリスチャンがそうではなかった場合、その事実は神のみ名についての自分たちの理解が間違っていることを示すものとなってしまい、エホバのみ名を呼び求める「エホバの証人」としての自分たちのアイデンティティを根本的に覆すことにもなってしまいます。
そこで「西暦二,三世紀の背教したクリスチャンたちは,ギリシャ語聖書の写本の写しを作る際にみ名を取り除き,聖書の翻訳を行なった時にもみ名を省いてしまいました」と言う改ざん説を作ることになったわけです。そのようなストーリーが無いと、エホバの証人の信条との辻褄が合わなくなるからです。
ですから、この神のみ名に関する陰謀論の是非は、「エホバの証人」というグループがそれによって立ちも倒れもする重要テーマとなっているのです。
エホバのみ名の改ざん説に対し『目ざめよ!』誌が反論する
このテーマの重要性を抑えた上で、いよいよこの陰謀論の真相に迫っていきますが、調べてみると大変興味深いことに、同じものみの塔から出版されている『目ざめよ!』誌が、この陰謀説に対する見事な反論をしていることがわかりました。その箇所を以下にご紹介したいと思います。(つまり、出版物同士の主張に完全な矛盾がある、ということです)
大勢の証人たち
西暦4世紀の写本よりも,さらに時代をさかのぼる写本が出て来ようとしていました。・・・その作成年代は3世紀にまでさかのぼります。ヨハネによる書の断片の一つは,西暦125年もの昔に作成されたものでした。それらの写本を,4世紀の写本,そして今日のわたしたちの聖書と比較した結果はどうでしょうか。一言半句の違いもないというわけではありませんでしたが,その音信に変わりはありません。どこであれ手が加えられた箇所は,すぐに明らかにされます。その音信は,はっきりと響き渡っています。
5,000を超すギリシャ語写本のおかげで,原本の本文を実際に復元する上で,手づるに事欠くことはありません。これら古代写本の研究にほとんど一生を費やしたフレデリック・ケンヨンは次のような結論を出しています。
「これら幾千部もの写本すべての起源をたどってゆくと,地球上の非常に多くの異なった土地や,非常な相違の見られる環境に到達する。ところが本文の変異は,全く末梢的な問題に関するものにすぎず,実質的なものではない。これはまさに,本質的に正しい方法で伝承が行なわれてきたことを示す驚くべき証拠である。
「また,これらの発見すべて,およびこの研究すべての全般的な結果が聖書の真正さの証拠となっていることを,最終的に見いだせたのは心強い限りである。そして,わたしたちは,実質的には損なわれていない,まがうことのない神の言葉を手にしていると確信しているのである」―「聖書の話」,136,144ページ。
聖書は二重の勝利者になります。聖書は本として生き続けるだけでなく,本文の高い純度を保っています。しかし,正確な本文が保たれてきたのは単なる偶然だ,という考えは道理にかなっていますか。二千年近くも前に完成され,激しい攻撃に直面した本が,幾千部もの古代写本という形で,依然として存在しているのは単なる偶然によると言えますか。しかもその古代写本の中には,原本ができてから25年以内に作成されたと思われるものもあるのです。これは,『われらの神のことばは永遠にたたん』と言われている方の力を示す豊かな証拠ではありませんか。―イザヤ 40:8。
実は、ここで引用した文章の内容こそが、新約聖書の信頼性について、写本の専門家の間で共有されている結論なのです。そしてものみの塔は、これらの文章を通して、聖書の信頼性についての専門家の結論に同意していることを、公に表明していることになるわけです。
上記の文章の中で、ものみの塔は、聖書が高い純度を保ってきたのは、単なる偶然ではなく、神の力と守りによる必然だとも主張しています。
「正確な本文が保たれてきたのは単なる偶然だ,という考えは道理にかなっていますか。二千年近くも前に完成され,激しい攻撃に直面した本が,幾千部もの古代写本という形で,依然として存在しているのは単なる偶然によると言えますか。・・これは,『われらの神のことばは永遠にたたん』と言われている方の力を示す豊かな証拠ではありませんか。
このものみの塔の主張に対しては、私もアーメンです。神は生きておられ、聖書を守ってきてくれたのです。ですから、もしも神が、新約以降の時代においても「エホバのみ名」を呼び求めるべき最重要な名として掲げておられるのなら、聖霊の導きと守りにより、ギリシア語写本からエホバのみ名が除き去られることを決して許したりはされなかったのではないでしょうか。
そして、上記の文章の中で、特に注目したいのは、この部分です。
「どこであれ手が加えられた箇所は,すぐに明らかにされます。その音信は,はっきりと響き渡っています。5,000を超すギリシャ語写本のおかげで,原本の本文を実際に復元する上で,手づるに事欠くことはありません。」
「どこであれ手が加えられた箇所は,すぐに明らかにされます」というのはどういうことでしょうか?それは、ある写本に改ざんが加えられたとしても、どうしても別の写本にオリジナルの文言が残ってしまうので、それらを比較することにより、改ざん箇所がわかってしまう、ということです。
例えば、2~3世紀のクリスチャンが当時現存していた1000の写本の内、100の写本に改ざんを行い、エホバのみ名を除き去ったと仮定しましょう。しかし、み名を含む残りの900の写本は残ってしまうので、それらを元に、改ざん箇所をすぐに明らかにすることができる、ということです。写本が多ければ多いほど、どうしてもオリジナルの文言の形跡が残ってしまうわけです。ですから、ものみの塔自身もこの点について「5,000を超すギリシャ語写本のおかげで,原本の本文を実際に復元する上で,手づるに事欠くことはありません。」と断定しているわけです。
以上の点を踏まえると、五千を越えるギリシア語写本の中に「エホバのみ名」が全く含まれていないという事実は何を示すのでしょうか?
それは、ギリシャ語のどの原本にも、初めから「エホバのみ名」は含まれていなかった、ということです。含まれていたのであれば、たとえ2~3世紀の背教したクリスチャンがみ名を除く改ざんを行ったとしても、一方でエホバのみ名を含むたくさんの写本も今日まで残っていたことでしょう。現存していた全ての写本からみ名を完全に除き去ることは、事実上、不可能だからです。ですから、5000を越すギリシア語写本のおかげで、私たちは「エホバのみ名を取り除く改ざんはなかった」と確信を持って言うことができるのです。「『われらの神のことばは永遠にたたん』」と書かれている通りです。
もう一つの点は、これまでの歴史の中で、逆に「主」を「エホバ」に書き換える改ざんもほぼ無かった、ということです。つまりイエスを主と信じるクリスチャンたちは、歴史的に、現代のエホバの証人と同じような理解を持たず、勝手にそのような改ざんをすることもなかった、ということです。

写本の研究を通して新約聖書の正確性に絶対的な確信を得たフレデリック・ケンヨン卿
改ざん問題をさらにわかりやすく考える
以上の説明からも、この問題の是非をある程度わかっていただけたかと思いますが、ここからは、「エホバのみ名を取り除く改ざんはなかった」という事実をさらにはっきりと理解していただくために、実際に「改ざんする側の視点」に立ってこの問題を考えてみたいと思います。。以下の三つの事例を想定し、順を追って説明していきます。
- 第一の例:ヨハネの福音書、写本数2、保管場所がエペソ教会のみの場合
- 第二の例:ヨハネの黙示録、写本数7、保管場所がエペソを含むアジアの七つの教会
- 第三の例:新約聖書27書、写本数、保管場所は多数
第一の例:ヨハネの福音書、写本数2、保管場所がエペソ教会のみの場合
最初に、エホバの御名を含むヨハネの福音書の写本が、原本が書かれたと考えられるエペソ周辺で二つだけ作成されたと考えましょう。そして、この二つを、エペソ教会が責任を持って保持していたと仮定します。
紀元二世紀になり、当時の教会の監督が、「エホバの御名を除いて主にするべきだ。後代に、エホバの御名を含むヨハネの福音書が残らないようにしよう」と考え、それを実行しようとしたとします。それは簡単ではないかもしれませんが、やろうと思えば不可能なレベルではありません。
なぜならこの場合、「エホバの御名を除き去る」行為に共謀するよう、あるいは「エホバの御名を除くべきだ」という考えに同意させなければならない人は、同じ教会内の少数に限定されるので、難易度としては物凄く高い、というレベルにはならないからです。
※ものみの塔が想定しているヨハネの福音書内の「エホバ」の出現数も10カ所程度です。
第二の例:ヨハネの黙示録、写本数7,保管場所が七つの教会の場合
では次に、ヨハネの黙示録の原本を写した写本が七つ作成され、イエスの指示通り、小アジア周辺の七つの地域に送られたとします。その後、それらの七つの写本が各地の教会で責任を持って保管されたとします。(これは仮ではなく、実際にそのようにされた可能性も高いと思われます)

写本が七つの異なる場所に行き渡るだけで、神の御名を除き去ることが不可能になる
では次に、ヨハネの黙示録の原本を写した写本が七つ作成され、イエスの指示通り、小アジア周辺の七つの地域に送られたとします。その後、それらの七つの写本が各地の教会で責任を持って保管されたとします。(これは仮ではなく、実際にそのようにされた可能性もあると思われます)
さて、二世紀に入り、エペソの教会の監督が「エホバの御名を除いて主にするべきだ。後代に、エホバの御名を含む黙示録が残らないようにしよう」と考えたとします。自分が監督するエペソの教会の写本はどうにかなるとしても、問題は他の六つの教会です。
ものみの塔が推定するヨハネの黙示録中の「エホバ」の推定出現個所は18カ所ですが、それら18カ所において、御名を除き去る改ざんをすべきだという持論を、他の六つの教会の監督に持ち掛けて、彼らを説得する必要があります。しかし、ここで二つの重大な問題に直面します。一つ目は、黙示録の中に、次のような警告が書かれていることです。
「19 また,この預言の巻き物の言葉から何かを取り去る者がいれば,神は,命の木から,また聖なる都市の中から,すなわち,この巻き物に書かれているものから彼の分を取り去られるであろう。」啓示(ヨハネの黙示録)22章19節、新世界訳
エホバは、この預言の書の中からどんな文字でも取り除くなら、その人は滅びると警告しているので、ユダ・イスカリオテのような人物でない限り、そのような意図的かつ深刻な罪に共謀しようとしたりはしないでしょう。
もう一つの問題は、2~3世紀の教会の監督たちは、多くの場合、筋金入りの信仰者であった、という事実です。というのは、当時のローマ帝国内では、迫害が断続的にあったため、クリスチャンとなることは、まして教会の監督となる者には殉教の覚悟が求められました。
キリストのためには命を捨てることも辞さないような覚悟を持つ教会の監督たちが、そんな意図的な罪に加担することなどあり得たでしょうか?万が一そのような人がいたとしても、六つの全ての教会の監督が、そのような罪に合意することなどあり得たでしょうか?それは、明らかに不可能だったことでしょう。
★補足事項:2~3世紀の背教について:確かに聖書には、使徒たちの死後に背教が起こるという警告がありますが、その背教の程度については、ものみの塔が仕切りに主張している「使徒たちの死後における大規模な背教」はありませんでした。実際には、使徒たちの信仰を忠実に継承する監督たちが各地域に起こされていき、教父と呼ばれるそのような人たちや教会と、背教的な異端との霊的闘いが、使徒たちの死後に鮮明化していった、というのが実際のところです。
このあたりの時代背景については、当時の教父たちの残した様々な著作が残っていますので、それらの著作を通して、はっきりと知ることができます。日本語で読めるものとしては、『使徒教父文書』『エウセビオスの教会史』あたりがお勧めですので、興味のある方は読まれることをお勧めします。
ものみの塔は、どういうわけか、紀元1~3世紀の教父たちの教えや情報をほぼ信者に教えないのですが、その理由はおそらく、もしも教父たちの情報を紹介すると、ものみの塔が仕切りに主張してきた「2~3世紀に教会全体が背教した」というストーリーが崩れるからなのでしょう。
※参考までに、二世紀のスミルナの教会の監督に「ポリュカルポス」という人がいましたが、彼を説得することはまず不可能だったことでしょう。彼は、使徒ヨハネの直弟子であり、殉教に至るまで忠実に歩んだことが伝承から証明されている高潔な人物です。そして、このような信仰の勇者たちが各地域の教会を監督していたというのが、西暦2~3世紀の時代背景なのです。
さて、これらの事例を実際に比較してみると、写本の数と保管場所が少数に限られている場合と、写本数と保管場所が多数に上る場合とでは、「エホバの御名を除き去る」という陰謀を成功させる難易度に、雲泥の差が生じる、ということがおわかりいただけたと思います。
ものみの塔が目ざめよ誌の中で「どこであれ手が加えられた箇所は,すぐに明らかにされます。・・5,000を超すギリシャ語写本のおかげで,原本の本文を実際に復元する上で,手づるに事欠くことはありません」と言っているのは、まさにこの事のゆえなのです。
さらにこの点について、新約聖書研究の権威であるブルース・M・メツガー博士によるコメントも紹介させて頂きます。
「『新約聖書が信頼できる、特に他の古代文献に比べて俄然信頼できるという理由は、今までに残されてきた写本の多さにあります。』と博士は答えた。
『どうしてそれが重要なのでしょうか』
『つまり、同一の写本が多いほど、特に違う場所から同一の写本が見つかった事例が多いほど、それぞれの写本を見比べて原本の内容を推察することがしやすくなります。・・』」(ナザレのイエスは神の子か、94ページ)
メツガー博士によれば、新約聖書が信頼できる理由は、(1)写本の多さにあること、(2)加えて同一の写本が違う場所から見つかる事例が多い、とされていますが、なぜそう言えるのか、これまでに挙げた二つの事例を通して、きっとその仕組みをお分かりいただけたと思います。
第三の例:新約聖書27書、写本数及び保管場所は多数
では最後に、実際の新約聖書の場合を想定して考えてみましょう。書簡数は27に上り、作成された写本数や保管場所の数がかなりの規模になっていたことは明らかです。その範囲や数を図で表し切ることは不可能ですが、ざっと表すと、以下のような感じになります。
エホバの証人の予測では、27の書簡の全てに「エホバのみ名」が含まれていたことになるので、二世紀初頭には、すでに「み名を含む」それらの写本が膨大な地域に広まっていたことになります。先ほどの事例2で挙げた通り、写本が七つの教会に広がっただけでも原本から神のみ名を除き去ることが不可能なほど困難になるのに、これだけの広範囲の地域に27の書簡がバラバラに広まっていった場合、果たしてどうやって「全ての写本からエホバの御名を除き去る」という陰謀を成功させることができたのでしょうか?
もしできたとすれば、当時の写本が保管されていた広範囲の地域全てのクリスチャンが、聖霊ではなく悪霊に満たされ、「エホバの御名を除かねば」という思いと、「どの個所を取り除いて主に置き換えるべきか」ということについての超自然的な確信と一致が与えられ、それらがある期間に漏れなく取り除かれた、という以外にはありません。
ただ、そんなことが起こりえないことは議論の余地のないことですし、万が一あったとしたら、その時に聖書のどこがまとめて改ざんされたのかが誰にもわからない、ということになるので、エホバのみ名の問題だけでなく、聖書全体の信頼性が覆ることになり、エホバの証人の「新世界訳」も共倒れすることになるでしょう。
つまり、エホバの証人が「み名を除く改ざん説」を主張することは、写本研究の事実に反しているだけでなく、実際には自分たちの聖書の根本的な信頼性に対しても攻撃する結果になってしまっているのです。
結論
では、以上の点からはっきりとわかることを改めて確認していきたいと思います。
まず、一世紀のクリスチャンは、主を呼び求める際に、神のみ名「エホバ」を用いることはしなかった、ということです。もし用いたのであれば、ギリシア語写本の中に神のみ名が含まれていたはずだからです。では、彼らが救いを求める時に、用いていた救い主の名はなんだったのでしょうか?その答えは、以下の聖句にはっきりと示されています。
「コリントにある神の会衆へ。皆さんはキリスト・イエスと結ばれて神聖なものとされ,招かれて聖なる人となりました。他のあらゆる場所でも,主イエス・キリストの名を呼んでいる人たちが招かれています。キリストはその人たちと私たちの主です。」第一コリント1章2節、新世界訳2019
一世紀のクリスチャンは、「エホバ」ではなく、「イエスの名」を呼び求めていた、これが聖書の記録からはっきりとわかる事実なのです。推測ではなく、事実です。父なる神ご自身が、新しい契約の時代において、救いを呼び求めるべき唯一の名として、主イエス・キリストの名を定められたのです。
使徒ペテロも次のように大胆に告白している通りです。
「さらに,ほかのだれにも救いはありません。人々の間に与えられ,わたしたちがそれによって救いを得るべき名は,天の下にほかにないからです」使徒4章12節、新世界訳2019
では最後に、この点から、初代教会の信仰についてどんなことがわかるでしょうか?以下の図をご覧ください。

信仰の対象の比較
まず、図の1行目は、旧約時代は、神の民が呼び求めていたみ名が「エホバ」であったこと、その対象が神であったことを示しています。これらは聖書的な事実です。
次に図の2行目は、新約時代において、神の民が呼び求めていたみ名が「イエス」であったことを表していますが、エホバの証人の理解においては、イエスは神ではなく天使長ミカエルです。そうなると、新約時代の神の民は、救いのために天使の名前を呼び求めていたことになり、神の名前を呼び求めていた旧約時代と、信仰の対象が釣り合いません。新しい契約の時代になり、呼び求める信仰の対象が格下げになってしまいます。
一方、キリスト教のように、イエスを神・エホバご自身と理解するとどうでしょうか?旧約時代と同様に、新しい契約下においても主なる神の名前を呼び求めていることになるので、信仰の対象が時代を通じて釣り合うのです。
つまり、新約時代のクリスチャンが、旧約のイスラエルがエホバの名を呼び求めたのと同じように主イエスの名を呼び求めていた、という事実は、聖書的にイエスが神であることを示すものとなるのです。
ものみの塔の歴史を見ると、初代会長のラッセルの時代は、今日のようにエホバの名を強調してはおらず、ただ三位一体・イエスの神性を否定していました。エホバの名を強調しだしたのは、そのもっと後からなのですが、今日のテーマを考えると、それは必然だったことがわかります。主イエスの名を呼び求めることと、イエスの神性とは霊的に結びついており、切り離すことができないからです。
ものみの塔は、イエスが神であることを否定した必然的な結果として、イエスの名を呼び求めることの霊的な意味がわからなくなり、その名を呼び求めることにおいて、初代教会と同じ信仰を持つことができなくなったのです。
この記事をご覧になる現役・元エホバの証人の方々の目がイエスに対して開かれて、心を開いて主イエスの名を呼び求めることができますように。主イエスの名によってお祈りします。


































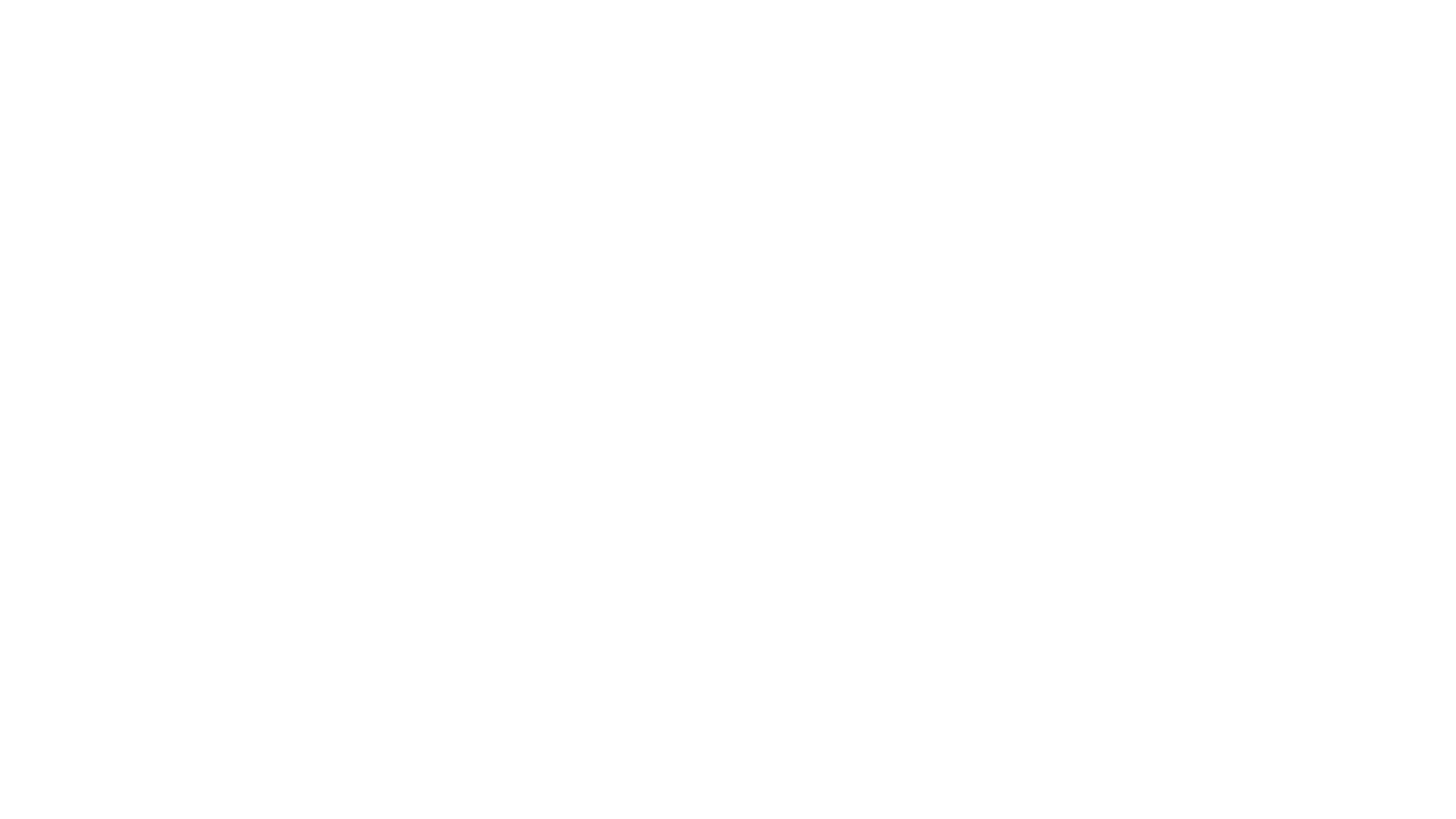













こんにちは、久保と申します。私は未信者ですが妻がエホバの証人です。
ですので中立的な立場でこちらのHPの主張を見させて頂いております。
第一コリント1章の引用から「つまり、イエスは神であり、エホバご自身だったのです。」
と結ばれていますが上記聖句の次、3節で「私たちの父である神と、主イエス・キリストから、皆さんに惜しみない親切が示され・・」とパウロが記述しています。
文脈から判断すれば明らかに「神」と「イエス」は別存在です。
非エホバの証人の訳も大概同じです。・・なので「イエスは神であり、エホバご自身だったのです」
は、おかしいと感じます。
加えて「ギリシャ語聖書にはエホバの御名を表す「YHWH」は一つも見出すことができないのです。」 これに関しては、「え、そうなの?!」だったのですが、
そうなると、ローマ10:13→「主の名を呼び求める者はだれでも救われる」のです。」(新共同訳)
に対し、呼び求めたいのですが「主の名」は何ですか?「主」さんですか?
・・となりますよね? それともこの「主」の部分は全て「イエス」を入れろ、という事でしょうか?
マタイ6:9・10はどうでしょうか。
「天におられるわたしたちの父よ、御名が崇められますように。御国が来ますように。御心が行われますように」(新共同訳) イエス=神ならば、「今はここに居るけど、天におられる私自身よ、私の名が崇められますように。私の王国が来ますように。私の望む事が行われますように。」、とイエスは言っている、という風に私には取れます。
とんだ「サイコ野郎」としか思えません。
妻がエホバの証人だから、こいつ洗脳されてるわ、とお考えかもしれませんが上記の様な私の疑問に
明確に答えて頂ける人が居ないので、発見したこちらにメール致しました。
もしお答え頂ける様でしたらお願い致します。
久保さん、こんにちは。
管理人代理の石川と申します。
奥様がエホバの証人なのですね。旦那様として奥様が関わっている信仰について広く調べようとする姿勢に敬意を表したいと思います。
また、当ホームページをご覧いただきありがとうございます。ご質問にも感謝します。
さて、久保さんからいただきましたご質問に答えていきたいと思います。
1.第一コリント1章3節について。
この節だけを見た場合は、神とイエスが別の存在であると思うでしょう。しかし、新約聖書の流れを理解した上でこの節を読むならば、つまり新約聖書全体の文脈に沿って読むならば、この節に書いてある神とイエスを完全に分けて読み込むことはありません。
私が現役のエホバの証人だった頃、イエスとエホバを別の存在だと教えられた知識に基づいて新約聖書を読んでいたために、新約聖書全体に流れる美しい真理に気がつくことができませんでした。
一節を切り取る方法で神を定義づけようとするなら、イエスが神である、または神でないと、自由に主張することが可能になってしまいます。
新約聖書を素直に読んでいく時に、久保さんが疑問に思われた第一コリント1章3節が輝きを纏って目に飛び込んでくると思います。
ちなみにですが、この章の最後でパウロはエレミヤ書を引用しつつ「誇るものは主を誇れ」と言っています。第一コリント1章の文脈を見るなら、パウロが誇れと言っている主は、主イエス・キリストのことを指していると理解できます。
新世界訳聖書では、「誇る人はエホバについて誇るべきです」となっていますね。エホバの証人が新約聖書にエホバの名を入れた事が逆に、イエスがエホバご自身であることを明らかにしてしまう箇所だと言えるでしょう。
2.ローマ10:13について。
新約聖書の筆者たちは、エホバとイエスが別の存在だと考えていませんでした。主のみ名を呼ぶ時に彼らはイエスの名を呼びました。エホバとイエスが別の存在であるなら、イエスの名を呼び求めることは偶像礼拝のリスクを犯すことになってしまいます。
神は唯一、真の神だからです。二神ではありません。
弟子たちが主としてイエスの名を呼ぶことにためらいはありませんでした。
聖書巻末の書で、使徒ヨハネはこう叫びました。
「アーメン、主イエス、来てください」(新世界訳)
聖霊によらなければ、誰もイエスを主であると告白することはできません。
3.マタイ6:9.10について。
この箇所は、私自身、エホバの証人だった頃に、三位一体を否定する根拠として使用していました。
まず、この箇所はイエスがご自身の祈りを披露したわけではないことに目を止めてみてください。
〜あなた方はこう祈りなさい〜
この箇所はイエスの話を聞いていたユダヤ人へのアドバイスです。
では、他の場面はどうでしょうか。イエスが父に杯を私から取り去ってくださいと祈っている場面です。
これは、イエスが二人一役を演じていたことになるのでしょうか。
この答えを知るには、新約聖書全体の文脈を素直に読み込むことが必要です。
ヨハネの福音書14:10で「わたしが父のうちにいて、父がわたしのうちにおられる・・・」と語られたことの意味を理解した時。アルファでありオメガである方を知った時。わたしたちが愛する前から愛してくださった方の愛が迫ってきます。
イザヤ53:11にあるように、イエスは久保さんのために血を流されたこと、ご自分の激しい苦しみの跡をご覧になって満足するのです。
イエスの名を信じる者に永遠の命が、キリストにあって神の子とされる特権が与えられるからです。
イエスが父のうちにおられて、父のうちにイエスがおられる。そして、イエスの名を信じる者のうちにイエスがおられて、信じる者がイエスのうちにいる。
新約聖書に描かれたこの真理を時間をとって深く考えることを強くお勧めします。
質問の答えになっておりますでしょうか。
これからも、是非ご自身で聖書の探究を続けてください。今も生きておられる神は、必ず応えてくださいます。
ご質問いただきありがとうございました。
是非、以下の記事もご参照ください。
https://gospel-jw.com/doctrine-jesus-lord/
https://gospel-jw.com/doctrine-trinity/
主イエスの恵みが久保さんと奥様とともにありますように。
石川様、とても丁寧な返信を頂き感謝いたします。
私は妻のおかげで今まで朧気にしか知悉していなかった聖書に関する知識が補完されました。その中でも驚いたのはユダヤ教の人々は未だに救世主を待っている、という点です。つまり彼らにとってイエスはただの人間、であって神絡みではない、というスタンス。私はイエスに対して妻や石川さんの様な愛が無いのでこの価値観も認めます。イエスに対する熱烈な愛情があるか無きかで新約聖書との向き合い方が変わる、と思いました。よく妻に怒られる件ですが→イザヤ53:11にあるように、イエスは久保さんのために血を流されたこと、ご自分の激しい苦しみの跡をご覧になって満足するのです。・・イエスが苦しみに耐え私(人類全て)の為に血を流して下さった・・ここでイエスが凄い方だ!と尊敬する為には彼が磔刑となりボコられて「痛っ!最悪!」となる存在であれば私は尊敬できます。しかし神と同等であったイエスにとってはどうだったのでしょうか?ドバーッと血を流してガクッと項垂れても「いや全然痛く無いんよ、何せ俺はお前ら凡人とは違うんだから」と思っていた訳ではないでしょうが、イエスにとって磔刑程度で苦しみなど感じない事が彼の神性の 証明である、と私は考えます。 この事で妻は「お前は人格が曲がっている、感謝の念が無い」と怒られます。ユダヤ教の日本人と話す事が出来ればこの点は賛同して頂けるとは思います。三位一体はどうしてもイエスを神と認めようとしないユダヤ教に向けてキリスト教界が強引にねじ込んだ教え、と説明されると得心がいきます。信仰とは個人の考えが最優先なので「じゃあ、お前はそう思ってれば?」と言われればチャンチャン、で終わりですが。
長文、失礼致しました。ありがとうございます。
久保さん、こんにちは。
管理人代理の石川です。
奥様を通して、久保さんの目が聖書に向けられていることを嬉しく思います。久保さんが感じておられる以下の疑問にお答えいたします。
【神であるなら痛み、苦しみを感じないはず】
神であっても心の痛みは感じます。旧約聖書の中で神が心に痛みを覚えている箇所を見出すことができます。エレミヤ31:20(わたしのはらわたは彼のためにわななき・・・)全能の神であっても心に痛みを覚えると表現されているのは興味深いことです。
では、肉体の痛みに関してはどうでしょうか。完全に神であり、完全に人であった方、イエスは磔における痛みを感じることなく血を流すことは可能だったのでしょうか。
答えは、可能であった、です。イエスは瞬時にご自分の傷を癒し、痛みを打ち消すことは可能でした。しかし、イエスが神としてのその力を使うことはありませんでした。
仮にイエスが十字架の上で苦しむ演技をしていたとするなら、それこそが神でない証拠となってしまいます。神は「偽る方ではない」からです。
イエスは神であるにもかかわらず、人として、全ての痛み苦しみをその身に受けました。彼はローマ兵に殺されたのではありません。十字架の上でその命を「捧げた」のです。
イエスは人が感じる心の痛み、肉体の痛み苦しみを経験されました。神である方が「人の子」としてこの地を歩まれたのです。
エホバの証人の聖書では改竄されている箇所ですが、旧約聖書のゼカリヤ12:10にはこう書かれています。
【わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見て、ひとり子を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、長子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣く。】
神ご自身が十字架の上で突き刺されました。興味深いことに、イエスの十字架上に書かれた罪状書きの頭文字はYHVH(エホバ)です。
神はこの地にこられ、人としてこの地を歩まれ、私たちの罪をその身に負いました。
イエス・キリストは久保さんへの愛を十字架の上から証されたのです。
※ここからは補足情報です。
数年前、ユダヤ人クリスチャンがイスラエルで詩篇を道ゆく人に無料で配りました。その詩篇にはイエスに関する預言に赤線が引かれていました。詩篇を受け取った1人のユダヤ教徒が血相をかえて走ってきて怒りながら言いました。「この詩篇にはイエスのことが書かれている!!」
ユダヤ人クリスチャンは言い返しました「赤線が引かれているだけです」
近年、多くのユダヤ人がイエスを信じるようになっています。三位一体なる神について、聖書に精通したユダヤ人たちがイエスが主であると告白すること以上に説得力のある言葉はありません。