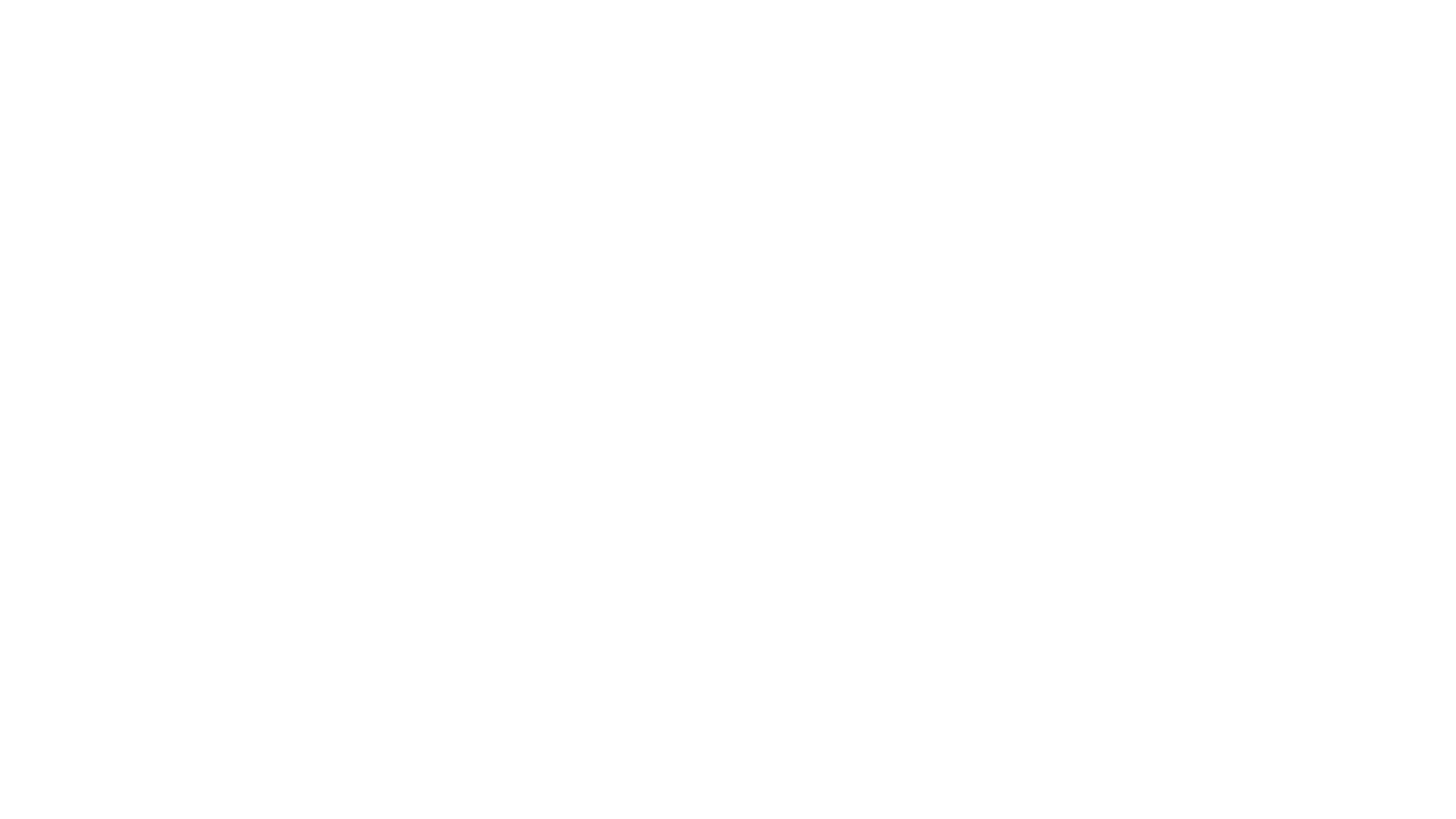三位一体⑤ 聖霊は神ですか?エホバの証人の反論に答える
今回の記事では、聖霊が人格な存在ではなく、神の聖なる力だとするエホバの証人の主張を一つ一つ取り上げ、それに対して聖書から答えていきたいと思います。
目次
聖書は聖霊が、神の手や指や息や水に似たものだと述べています
ものみの塔の主張
聖霊は神の手や指や息です
「聖書は、神の霊のことを、神の「手」や「指」や「息」であると述べることにより、聖霊が人格的存在ではないことを明らかにしています。(出エジプト15:8,10)人間の手は、脳や体から独立して機能することはできません。同じように、聖霊も神の指示なくしては作用しません。」(ルカ11:13)―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
参照されている聖句は以下の通りです。
「そして,あなたの鼻孔の一息によって水は盛り上げられ, せき止められた洪水の水のように静止した。 逆巻く水が海のただ中で固まった。・・・10 あなたはご自分の息を吹きかけ,海は彼らを覆った。 彼らは荘厳な水の中に鉛のように沈んだ。」(出エジプト記 15:8,10)
「それで,あなた方が,邪悪な者でありながら,自分の子供に良い贈り物を与えることを知っているのであれば,まして天の父は,ご自分に求めている者に聖霊を与えてくださるのです」(ルカ 11:13)
聖霊は水に似たものです
聖書の中では、聖霊が水に似たものであると述べられていたり、信仰や知識と関連付けられていたりします。こうした点はいずれも、聖霊が人格的存在ではないということを示しています。―イザヤ44:3、使徒6:5、コリント第二6:6。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
参照聖句は以下の通りです
「わたしは渇いた者に水を,滴り出る流れを乾いた場所に注ぎ出すからである。わたしはあなたの胤にわたしの霊を,あなたの末孫にわたしの祝福を注ぎ出す。」(イザヤ 44:3)
「こうして話されたことは大勢の者全員の喜ぶところとなった。それで彼らは,信仰と聖霊に満ちた人ステファノ,およびフィリポ,プロコロ,ニカノル,テモン,パルメナ,またアンティオキアの改宗者ニコラオを選び出した。」(使徒 6:5)
反論:イエスも「言葉」「道」「真理」と述べられています
聖霊が、神の「手」や「指」であると聖書が述べているからと言って、聖霊が人格的存在でないことが証明されるわけではありません。たとえば、聖書はイエス・キリストが神の「ことば」であると述べていますが、それはイエスが非人格的存在であることを示しているわけではありません(ヨハネ1:1、啓示19:13)。
またイエスはご自分のことを、「道・真理・いのち」だと宣言しました(ヨハネ14:6)。道や真理やいのちは人格的存在ではありませんが、それによってイエスの人格性は否定されません。それらはあくまで、イエスの役割・特質を表す象徴的な称号なのです。同じように、聖霊が「神の指」だからといって、聖霊が非人格的存在であることが証明されるわけでは無いのです。
「人間の手、脳や体から独立して機能することはできません。同じように、聖霊も神の指示なくしては作用しません。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
この点については、父と聖霊との間の序列を示しているに過ぎません。三位一体の神には、父→子→聖霊、という序列があるので、「聖霊」だけでなく「子」についても、基本的に父の指示にしたがって行動されますが、その事実が「子」の人格性を否定するわけではありません。聖霊についても同様です。
聖霊の名はどこにも見当たりません
ものみの塔の主張
「聖書 に は,エホバ 神 の 名 や み子 イエス ・ キリスト の 名 が 出 て き ます が,聖霊 の 名 は どこ に も 見当たり ませ ん。(イザヤ 42:8。ルカ 1:31)」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
参照されている聖句は以下の通りです。
「わたしはエホバである。それがわたしの名である。わたしはわたしの栄光をほかのだれにも与えず,わたしの賛美を彫像に[与える]こともしない。」(イザヤ 42:8)
「見よ,あなたは胎内に[子]を宿して男の子を産むでしょう。あなたはその名をイエスと呼ぶのです。」(ルカ 1:31)
反論:聖霊の名は「エホバ」です
聖霊の名は、次の聖句で表されています。
「それゆえ,行って,すべての国の人々を弟子とし,父と子と聖霊との名において彼らにバプテスマを施し」(マタイ28:19)
「Go, therefore, and make disciples of people of all the nations,+ baptizing them+ in the name of the Father and of the Son and of the holy spirit,」(NWT)
この聖句での「名」は、「Name」(単数形)であり、複数形ではありません。つまりイエスは、「父の名」「子の名」「聖霊の名」という三つの名に言及したのではなく、「父・子・聖霊」によって表される「一つの名」によってバプテスマを施すよう命令したのです。
ではその名とは何でしょうか?言うまでもなく、父の名は「エホバ」ですが、「子」と「聖霊」も、父と同一の名によって表されるということは、子と聖霊の名も「エホバ」だということになります。つまり、エホバという名は、父だけの名ではなく、三位一体の神の御名なのです。(ヨハネ12:41、ペテロ第一1:11も参照)
また、へブル的な文脈では、「名」は当人の本質・実質を表すものと理解されます。ですから、イエスが「父・子・聖霊の名によって」と言った時、イエスはその名の具体的な固有名について言ったのではなく、父・子・聖霊によって表される一つの本質・実体について語ったものと考えられます。もちろんそれは、神としての特質・実質を表していることでしょう。
聖霊の名によるバプテスマは人格性を意味しません
ものみの塔の主張
ここで、マタイ28章19節に関する、ものみの塔の側の反論を確認しておきたいと思います。
「聖書 で は,「名」が 権威 や 権力 を 表わし て いる 場合 が あり ます。(申命記 18:5,19‐22。エステル 8:10)英語 に も,「法 の 名 に おい て」と いう 表現 が あり ます が,それ は 法律 が 人格 的 存在 で ある こと を 意味 し て いる の で は あり ませ ん。聖霊 の「名 に おい て」バプテスマ を 受ける 人 は,神 の ご意志 が 成し遂げ られる うえ で の 聖霊 の 権威 や 役割 を 認め ます。―マタイ 28:19。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
参照されている聖句は以下の通りです。
「彼は,すなわち彼とその子らとは,あなたの神エホバがあなたのすべての部族の中から選び,立って常にエホバの名において仕えるようにさせた者だからである。」(申命記 18:5)
「そして,彼がわたしの名において話すわたしの言葉に聴き従わない者には,わたしがその者に言い開きを求めることになる。」(申命記 18:19)
「こうして,彼はアハシュエロス王の名で書き,王の認印つきの指輪で印を押すことをし,しゅん足の雌馬の子,王の奉仕に用いられる早馬に乗る,馬上の急使の手により書状を送った。」(エステル 8:10)
「それゆえ,行って,すべての国の人々を弟子とし,父と子と聖霊との名において彼らにバプテスマを施し,」(マタイ 28:19)
まず、マタイ28章19節において、「聖霊の名」と言われているからと言って、それは聖霊が人格的存在であることを意味しているわけではない。例えば、英語 に も「法 の 名 に おい て」と いう 表現があるが、法は人格的存在ではない、と論じられています。
しかし、「法の名において」は現代の米国での話であって、聖書的な文脈ではないので、論拠としては不十分です。また、実際にこの文章の中で参照されている聖句の全ては、「エホバの名」「アハシュエロスの名」のように、人格的存在の「名」について言及しています。つまり、実際に聖書の中で「誰々の名」という表現が、非人格的な存在にも用いられている事例を示すことができていないので、いづれにしても、反論としては不十分です。
「聖霊 の「名 に おい て」バプテスマ を 受ける 人 は,神 の ご意志 が 成し遂げ られる うえ で の 聖霊 の 権威 や 役割 を 認め ます。」
既に説明した通り、マタイ28:19の「父・子・聖霊の名によるバプテスマ」の「名」は単数形であるため、それは三位一体の一人の神の名によるバプテスマを意味しています。ですから、聖霊の権威や役割を認めることは確かに大切なのですが、この文脈では、聖霊の名の意味を他の二者と分けて論じることよりも、父・子・聖霊によって表される一つの名について語ることがより大切だと言えるでしょう。
ステファノは聖霊を見ませんでした
ものみの塔の主張
「クリスチャン の 殉教 者 ステファノ は 奇跡 的 に 天 の 光景 を 目 に し まし た が,見え た の は エホバ と イエス だけ で,聖霊 は 見え ませ ん でし た。「彼 は 聖霊 に 満ち,天 を 見つめ て,神 の 栄光 および イエス が 神 の 右 に 立っ て おら れる の を 目 に し」た,と 聖書 は 述べ て い ます。(使徒 7:55)ですから,聖霊 は 神 の 活動 する 力 で あり,ステファノ は その 聖霊 の 力 に よっ て 幻 を 見る こと が でき た の です。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
それは聖霊の非人格性の根拠とはなりません
聖書時代の預言者が天を垣間見た体験は複数記録されていますが、その時に必ずしも、三位一体の神の全てが登場しているわけでありません。例えば、黙示録5章における天での礼拝の場面でも、聖霊は登場しません。(ただし4章によれば、その光景は聖霊の導きによってヨハネに啓示されています)
一方、黙示録1章の幻の冒頭では、父・子・聖霊の三位格が、人格的主体をもって登場します。
「あなた方に,「今おられ,かつておられ,これから来られる方」からの,またそのみ座の前にある七つの霊からの,5 そして,「忠実な証人」,「死人の中からの初子」,「地の王たちの支配者」であるイエス・キリストからの過分のご親切と平和がありますように。」(啓示1:4-5)
ですから、天の幻で聖霊が登場するかどうかは、聖霊の役割によって変化するその時々の状況によるのです。
聖霊の役割の問題
補足として、ステファノが天を見上げた時に、聖霊を見なかったのは自然なことです。なぜなら、彼が殉教したのはイエスの昇天後ですが、イエスは昇天の前に、自分の代わりに弟子たちの元へ聖霊を遣わすと約束していたからです。つまり、ペンテコステの日以降、聖霊の活動の中心は、イエスに代わって地上へと移っていたのです。
また聖霊の役割は、自分が栄光を受けることではなく、父と子が栄光を受けるように働くことです。そのような聖霊の役割は、聖書全体の文脈から明らかなことです。ですから、ステファノの殉教の時における聖霊の役割は、その時の彼を満たし、父と子の栄光を見せることだったのです。
初期の弟子たちは聖霊の人格性を信じていませんでした
誤っ た 考え: イエス の 使徒 や 初期 の 弟子 たち は 聖霊 が 人格 的 存在 で ある こと を 信じ て い た。
真実: 聖書 も 歴史 の 記録 も その よう な こと は 示し て い ませ ん。ブリタニカ 百科 事典(英語)に は こう あり ます。「聖霊 は 別個 の 神聖 な 人格 的 存在……と いう 定義 は,西暦 381 年 の コンスタンティノープル 公会議 に おい て 決定 さ れ た」。これ は,最後 の 使徒 が 亡くなっ て から 250 年 以上 後 の 出来事 でし た。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
いつものことですが、このようなものみの塔による文献引用の仕方は、読者に対して不適切な誤解を与えます。まず、ブリタニカ百科事典の原文はこうなっています。
The definition that the Holy Spirit was a distinct divine person equal in substance to the Father and the Son and not subordinate to them came at the Council of Constantinople in ce 381, following challenges to its divinity. https://www.britannica.com/topic/Holy-Spirit
聖霊が父と子と同質であり、彼らに従属しない独立した神格であるという定義は、その神性に対する異議申し立てを受けて、西暦381年のコンスタンティノープル公会議で確立された。東・西両教会はその後、聖霊を父と子との間の絆、交わり、あるいは相互の愛と見なしてきた。
ものみの塔の文章と引用の仕方を読むと、あたかも聖霊の人格性の定義が、381年の公会議から始まったかのような印象を受けますが、それは事実ではありません。「その神性に対する異議・申し立てを受けて」とある通り、その前から聖霊の神性・人格性への理解がまず前提としてあり、それに対する神学的反論がなされて会議で議論されたのが381年のことであり、その際に聖霊の神性(人格性)への理解・教義体系が確立された、という流れです。
これは三位一体論だけでなく、多くの教理について言えることですが、最初は明確な教理的定義が無かったテーマが、時代の経過と共に異端的な誤った教えにさらされ、それに反論する形で正しい聖書的な教え・定義が確立していく、ということがあります。み子の神性や聖霊の神性についても、そのようなプロセスが起こった、ということなのです。
聖書を読むと、聖霊の人格性を示す箇所がとても多く登場します。その最大の理由は、初期の弟子たちが、聖霊の人格性を認めていたからに他なりません。
ヨハネ第一5章7~8節は偽筆であり三位一体の証明とはならない
誤っ た 考え: 「御霊(みたま)」つまり 聖霊 は 人格 的 存在 で あり,「ジェームズ 王 欽定 訳(きん て い やく)」聖書 の ヨハネ 第 一 5 章 7,8 節 が 述べる とおり,三位一体 の 一部で ある。
真実: 「ジェームズ 王 欽定 訳」聖書 の ヨハネ 第 一 5 章 7,8 節 は こう なっ て い ます。「天 に おい て……御父(みち ち)と 御言葉(みことば)と 御霊……この 三つ は 一つ なり。また,地 に おい て 証(あかし)する もの は 三つ」。しかし,研究 者 たち に より,これら の 言葉 が 使徒 ヨハネ に よっ て 書か れ た もの で は ない こと,それゆえに 聖書 に 含め られる べき で は ない こと が 判明 し まし た。ブルース ・ M ・ メツガー 教授 は こう 書い て い ます。「これら の 言葉 が 偽筆 で あり 新約 聖書 の 中 に 含め られる べき 理由 が 一切 ない こと は 明白 で ある」。―「ギリシャ 語 新約 聖書 の 本文 に 関する 注解」(英語)。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
エホバの証人の統治体は、ヨハネ第一5:7-8が偽筆であることを主張する根拠として、聖書学者のブルース・M・メツガー博士の言葉を引用しています。メツガー博士は、大変有名な聖書学者であり、ものみの塔も度々出版物で、博士のコメントを引用していますが、メツガー博士はれっきとした三位一体論者であるため、上記のような引用の仕方は、読者に誤解を与えかねません。
以下は、「リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社」での、メツガー博士のコメントです。
「エホバの証人の信者が訪問伝道に来て、『英欽定訳聖書には、ヨハネの手紙第一5:7~8節に、「父とことばと御霊である。この三つが一つとなる」とありますが、最古の写本にはこうした文章はありません。だからあなたの聖書は間違っています』と言ったとしましょうか。
これは事実だと思います。・・・しかし、だからといって、聖書ではっきりと証言されている三位一体の教理が否定されることにはなりません。・・・パウロはコリント人への手紙第二の最後で『主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊なる交わりが、あなたがた全てとともにありますように』と書いています。三位一体を示す聖句は他にもたくさんあります。」
このように、ものみの塔が彼らの教理を擁護するために行う文献引用は、読者に誤解を与えるような内容が目立ちます。
聖霊の人格性を表す表現は全て「擬人法」です
ものみの塔の主張
「聖書 が ときどき 聖霊 を 擬人 化 し て いる から と 言っ て,聖霊 が 人格 的 存在 で ある こと の 証拠 に なる わけ で は あり ませ ん。聖書 は 知恵 や 死 や 罪 も 擬人 化 し て い ます。(箴言 1:20。ローマ 5:17,21)例えば,知恵 に は「働き」が あっ て「子供 ら」が いる と 述べ られ て い ます。また,罪 は 人 を たぶらかし,殺し,貪欲 を 生み出す,と 描写 さ れ て い ます。―マタイ 11:19。ルカ 7:35。ローマ 7:8,11。」―JW.ORG「聖霊とは何ですか?」
聖書の文脈上「擬人法」だけでは説明がつかない
確かに聖書は、知恵や死や罪などの用語を擬人化しています。しかし、それらの用語を人格的な存在として理解する神学者はいません。なぜなら、それらの用語が擬人化されるとしても、その言葉の本来的な意味が聖書的文脈において明らかだからです。
しかし、聖霊の人格性については、ほとんどの神学者がそれを認めているのはなぜでしょうか?それは、既に本記事で説明してきた通り、聖霊の人格性を示す表現はあまりにも多く、聖書的な文脈上において、「擬人法」として見做せるレベルを明らかに越えているからです。
無限の神を有限な人間の知性で計ることはできない
キリストの神性においても、聖霊の人格性の理解においても、エホバの証人の解釈の問題の本質は同じです。それは、人智を超越した無限の神の存在を、有限な人間の知性に押し込めて理解しようとすることです。
私たち人間が、神に関して、真理の全体に関して理解できていることはごく僅かなものです。この物質世界の中についてでさえ、人間が知り得ていることは僅かなものであり、まして神が臨在しておられる霊の領域についてはなおさらのことです。
確かに、この目に見える世界の中には、水のような役割をする人格的存在はないかもしれません。しかし、深遠な神の実体においてもそのようなことがあり得ないと断定する根拠は何もありません。被造物の中に存在する制約に、万物の創造主が制限されることは無いからです。
「あなたは神の深い事柄を見いだすことができようか。 あるいは,全能者の極限までも見いだすことができようか。」(ヨブ 11:7)
「エホバは大いなる方,大いに賛美されるべき方。その偉大さは探りがたい。」(詩篇145:3)
「ああ,神の富と知恵と知識の深さよ。その裁きは何と探りがたく,その道は[何と]たどりがたいものなのでしょう。」(ローマ8:33)
大切なのは、組織の出版物によってではなく、人の悟りや知恵によってではなく、生ける神の言葉と聖霊の導きによって、真理を悟ることなのです。
“どうか、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなたがたに与えてくださいますように。” エペソ人への手紙 1章17節
聖霊の役割を横取りした統治体
最後に、統治体の立ち位置についての、霊的な考察をお話させて頂きたいと思います。主が語られた通り、聖霊には真理を教える役割があります。つまりイエスを信じる者は、聖書を読む時に、正しい理解を得るために、聖霊の導きを受けることができるのです。しかし統治体は、正しい理解を得るためには、自分たちの助けが必要だと主張します。自分たちの権威を認めなければ、ハルマゲドンで滅ぼされるとまで主張します。この主張は、聖霊の役割を横取りするものです。
統治体・ものみの塔協会は、聖霊の人格性を否定することにより、そこで空洞になった聖霊の人格性という椅子に、自らを置くことになってしまったのです。つまり、霊的な構図としては、統治体は聖霊の代わりとなったのです。
その結果として、過去のあるコンテンツでは、出版物の勉強を通して「忠実で思慮深い奴隷と間接的な関係を持つことができます」ということを言い出したほどです。聖霊の交わり、という言葉を「聖霊にあずかる」と言い換え、代わりにその交わりを「統治体との交わり」にしてしまったのです。

生徒(ギレアデ学校の)は学校生活の中で、この図書室で勉強できる時間を楽しみにしています。静かで落ち着いた環境で、忠実で思慮深い奴隷と間接的な関係を持つことができます。出典:JWブロードキャスティング、マンスリープログラム:2018年7月
この非聖書的な霊的構図に、多くのエホバの証人が気付いていくことができますように