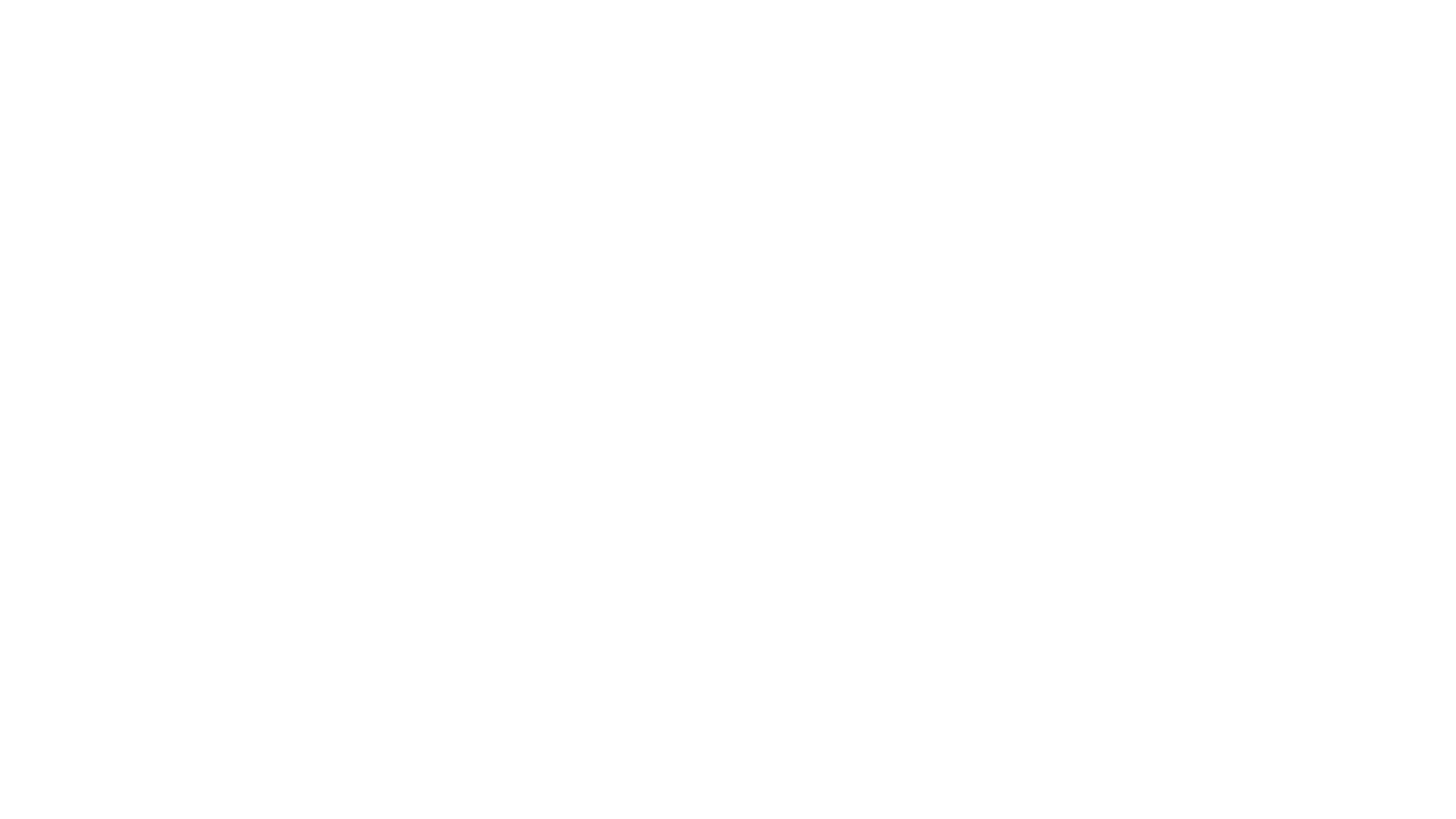三位一体④ 聖霊は神の聖なる力か?それとも人格的主体を持つ神か?
2019年、エホバの証人の統治体は新たな改訂版の新世界訳聖書を発行しました。その改訂版でなされた最も重要な翻訳の変更点の一つが、「聖霊」を多くの箇所で「聖なる力」としてしまったことです。改訂版の特色は、現代人にとってわかりづらい多くの表現を分かりやすい表現に変えたことにありますが、そこにはリスクもありました。そのリスクとは、聖書翻訳を人間の理解に合わせ過ぎると、神の言葉が伝えている本質的な意味から逸れてしまう、という問題です。
聖霊を聖なる力と翻訳したこの変更は、エホバの証人が、深遠な神の実体を人間的な理解へ閉じ込める方向へと、さらに舵を切ったことを如実に表した出来事だったと言えるでしょう。聖霊は神なのか、それとも「神の聖なる力」なのか、本記事で明らかにしていきます。
「それで,行って,全ての国の人々を弟子としなさい。父と子と聖なる力の名によってバプテスマを施し,」マタイ28:19、新世界訳、2019年改訂版
目次
エホバの証人が聖霊の人格性を否定する真の霊的理由とは?
エホバの証人とキリスト教との聖霊に関する議論は、聖霊の人格性の有無に集中します。エホバの証人の側は、「聖霊は神の聖なる力(活動力)であって、人格的な存在ではないと強く主張します。キリスト教サイドはその逆で、聖霊が人格的な主体を持つ神だと主張します。
本記事を進めていく中で、改めて、エホバの証人がなぜ聖霊の人格性を否定し続けるのか、その根本的な理由を思い巡らしました。それは、表面的な理由というよりも、組織の統治体の深層心理や、そこに働く霊的存在が、聖霊の人格性を否定したがる理由のことです。
そこではっきりとわかったことは、その最も単純かつ重要な理由は、やはり三位一体の否定にあるのです。というのも、もしも聖霊の人格性を認めてしまうと、父と聖霊の双方が神であることになり、「複数の者が一体となって一人の神となる」という三位一体的な神理解への扉を開くことになるからです。それはエホバの証人にとってはパンドラの箱であり、その箱を開くことは組織にとっては崩壊と死を意味するのです。
筆者はどのように聖霊が神だと信じるようになったのか
次に、聖霊の人格性に関する議論の要点を抑えながら、元エホバの証人であり、本記事・サイトの筆者である私が、聖霊の人格性について、どのように目が開かれていったのかをお話したいと思います。
エホバの証人が「聖霊は神の活動力だ」と主張する聖書的な理由は、聖書の中で「満たされる」「注がれる」などの非人格性を示唆する表現が、聖霊に対して多く用いられるからであり、それゆえに「人格を持つ存在にそのような表現が適用されるはずが無い」という結論に至るのです。
“わたしは潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、わたしの霊をあなたの子孫に、わたしの祝福をあなたの末裔に注ぐ。” イザヤ書 44章3節 聖書 新改訳2017
確かに、エホバの証人の主張もわからないでもありません。「聖霊が注がれる」という表現は聖書から自然に理解できますが、「イエスが注がれる」「父が注がれる」という表現はないですし、もしあっても違和感を感じるかもしれません。ですから私自身、エホバの証人に居た時には、聖霊が聖なる力であることに対して疑いを持つことはありませんでした。
では、聖霊の人格性を示すような箇所はどう理解するのでしょうか?確かに聖書を読むと、キリスト教側が主張する通り、聖霊の人格性を示すかのような箇所もたくさんあります。しかし、ものみの塔の教えによれば、聖書は人格の無い存在を、人格を持っているかのように表現する「擬人法」も多用しているので、聖霊の人格性を示唆する全ての箇所も、同様に擬人法だとされています。
例えば、「罪」は人格的存在ではありませんが、「 人 を たぶらかし,殺し,貪欲 を 生み出す」とも 描写 さ れ て い ます。(マタイ 11:19。ルカ 7:35。ローマ 7:8,11)このような教えによって、聖霊が神の聖なる力であることを、私は何の疑いもなく信じてきたわけです。
ところがその後、イエスの神性に対してまず目が開かれた私は、自ずと「三位一体」という概念に対しても目が開かれていきました。そして、組織の教えではなく、聖書そのものから、聖霊の人格性について改めて読み直していくことを始めたのです。
そして、聖霊の人格性についての一連の聖句を見直していく中で、私は気づいていきました。それは、聖霊の人格性を示す表現はあまりにも多く、また多様であり、その全てを「擬人法」として片づけるのは無理がある、ということでした。実際に、聖霊は私たちを助け、導き、教え、話し、証言し、執り成し、悲しむことも、欺かれることもあるのです。
このようにして、私は聖霊の人格性を信じるに至ったわけですが、振り返ってみると、ものみの塔がなぜ聖霊の人格性を否定しているのか、その理由がなんとなくわかります。それは、聖霊という神の深遠な実体を、あくまで人間の知性で理解できる範囲内で捉えようとしているためだと思います。
つまり、ものみの塔、および統治体にとっては、「注がれる」等の非人格的な特徴を示唆する聖霊が、同時に人格的な特徴も併せ持つ、ということが理解できないし、理解しようともしないのです。なぜなら、私たちが生きている自然界の視点においては、「注がれる」と同時に「人格もある」という存在は皆無だからです。
しかし、本シリーズにおいて繰り返し述べているように、神の実体やその深遠さは人知を超えたものであって、地上の人間の限られた知性で理解しきれるものではないと聖書は教えています。万物の創造主の実体を、被造物の制約の中で捉えることはできないのです。
ですから私たちは心を開いて聖書を読み、「自分が理解できるか」の前に、「聖書が何と言っているのか」という視点で神を捉える必要があるのではないでしょうか?そうでなければ、聖書がどれだけ聖霊の人格性について証言をしても、その真理をいつまでも受け入れることができなくなってしまうでしょう。
聖霊の人格性① 父なる神と子なる神と同列に置かれている
ここからはいよいよ、聖霊の人格性についての聖書の証言を取り上げていきたいと思います。最初にお伝えしたい点は、聖霊は複数の箇所において、「父なる神」「子なる神」と共に、人格的主体を持つ存在として同列に置かれている、この三者がひとまとまりの存在として表現されている、という点です。そのような場合、父と子だけは人格的存在なのに、聖霊だけは非人格的存在だというのは、不自然です。
「それゆえ,行って,すべての国の人々を弟子とし,父と子と聖霊との名において彼らにバプテスマを施し,」(マタイ 28:19)
ここで父と子と聖霊の名、と表現されている事実は、聖霊の人格性を明瞭にしています。「名」という表現が、このような文脈で非人格的存在に用いられる事例が、聖書中にまず無いからです。しかも、ここでの「名」は単数形なので、父・子・聖霊によって表される一つの名を意味していますが、へブル的文脈においては、「名」はその人の実質・本質を表すものです。聖霊が、父・子と同じ実質・本質を持つのであれば、聖霊が人格的存在であることは明らかです。
「主イエス・キリストの過分のご親切と神の愛,ならびに聖霊にあずかることが,あなた方すべてにありますように。」コリント第二13:14
ここで「あずかる」と訳されているギリシア語は「コイノニア」という言葉で、「交わり・交流」を意味する言葉です。つまりパウロは、人格的存在である聖霊との交わりを意図して、この表現を用いたのですが、その人格性を否定するものみの塔は、「交わり」という意味合いを避け、「あずかる」という訳出をしてしまっています。
(改ざんや誤訳とはまでは言えないかもしれませんが、コイノニアという言葉は相互的な交流が中心的な意味となるので、「あずかる」という一方的なニュアンスの表現は、原文への忠実さではなく、エホバの証人の教理を反映した明らかな意訳と言えるでしょう)
「あなた方に,「今おられ,かつておられ,これから来られる方」からの,またそのみ座の前にある七つの霊からの, 5 そして,「忠実な証人」,「死人の中からの初子」,「地の王たちの支配者」であるイエス・キリストからの過分のご親切と平和がありますように。」啓示1:4~5
ここでは聖霊が「七つの霊」と表現されていますが、読者への恵みと親切と平和の出どころが、「父・子・聖霊から」となっています。つまり、聖霊にも父・子と同様の人格的主体があることが読み取れます。
聖霊の人格性② もう一人の助け主(ヨハネ14章6節)
助け主:パラクレートス
「わたしは父にお願いします。そうすれば、父はもうひとりの助け主をあなたがたにお与えになります。その助け主がいつまでもあなたがたと、ともにおられるためにです。」(新改訳)
「そしてわたしは父にお願いし,[父]は別の助け手を与えて,それがあなた方のもとに永久にあるようにしてくださいます。17 それは真理の霊であり,世はそれを受けることができません。」(新世界訳:エホバの証人)
「And I will ask the Father and he will give you another helper* to be with you forever,」(NWT:エホバの証人)
ここでイエスは、自分が天へ戻る代わりに「もうひとりの助け主」(別の助け手)を遣わすという約束を、弟子たちに対して与えました。
「助け主」と訳されるギリシャ語は「パラクレートス」であり、「慰め主、助言者、助け主、とりなす者、弁護者」などの意味があり、非人格的な存在に対して用いられることはありません。さらに、「助け主」の人格性は、続く14~16節までの一連のメッセージを通して、全面に表現されています。
「しかしやはり,わたしはあなた方に真実を告げます。わたしが去って行くことはあなた方の益になるのです。わたしが去って行かなければ,助け手は決してあなた方のもとに来ないからです。しかし,去って行けば,わたしは彼をあなた方に遣わします。 8 そして,その者が到来すれば,罪に関し,義に関し,裁きに関して,納得させる証拠を世に与えるでしょう。」(ヨハネ16:7~8、新世界訳)
「しかし,その者,すなわち真理の霊が到来するとき,あなた方を真理の全体へと案内するでしょう。彼は自分の衝動で話すのではなく,すべて自分が聞く事柄を話し,来たらんとする事柄をあなた方に告げ知らせるからです。 14 その者はわたしの栄光を表わすでしょう。彼はわたしのものから受けて,それをあなた方に告げ知らせるからです。」(ヨハネ16:13~14、新世界訳)
もうひとり:アロス
さらに注目すべきは、「もうひとりの助け主」の「もうひとり」(別の)という言葉であり、ギリシャ語の原文では「アロス」という言葉が用いられています。
ギリシャ語の「別の・もうひとつの」という言葉には、二通りの言い方があります。一つ目は「アロス」で、「同じ種類あるいは同質の、もう一つ」という意味があります。二つ目は、「ヘテロス」で、「質の違う、もう一つ」という意味となります。
たとえば、カフェで店員さんに水のおかわりを頼む時に「もう一杯」という場合には、全く同じ水のことを意味しますので「アロス」となります。しかし、「別の」ドリンクを注文する場合には「ヘテロス」が用いられるのです。
以上の言語的な意味を念頭に置けば、イエスが聖霊に対して「アロス」を用いたという事実は、聖霊がイエスと全くの同質の「人格的な存在」であることを示しています。またその点は、イエスがマタイ28章で「父と子と聖霊の名(単数形)」と言った事実とも調和します。
聖霊の人格性③ 聖霊には知性・感情・意志がある
人間の精神・心の構成要素は、一般的に「知・情・意」として知られており、人格的な存在の特徴とも言えます。聖書を丁寧に読んでいくと、聖霊の人格的な特徴として、この知情意が見事に多くの箇所で表現されています。
聖霊は知性を持つ
「それでも,心を探る方は,霊の意味するところが何かを知っておられます。それは神にしたがいつつ聖なる者たちのために願い出ているからです。」(ローマ 8:26-27)
「神はそれを,ご自分の霊によって,このわたしたちに啓示されたのであり,霊がすべての事,神の奥深い事柄までも究めるのです。」(コリント第一 2:10)
聖霊は悲しむ
「しかし,彼らは反逆し,その聖霊に痛みを覚えさせた。そこで,[神]は彼らの敵に変じ,自ら彼らと戦われた。」(イザヤ 63:10)
「また,神の聖霊を悲しませることのないようにしなさい。贖いによる釈放の日のために,あなた方はそれをもって証印を押されたのです。」(エフェソス 4:30)
聖霊には意志がある
「また,彼らはフリギアとガラテア地方を回った。アジア[地区]でみ言葉を語ることを聖霊によって禁じられたからである。」(使徒 16:6)
「さらにある人には強力な業の働き,ある人には預言すること,ある人には霊感のことばを識別する力,ある人には種々の異言,そしてある人には異言を解釈する力が与えられています。しかし,これらのすべての働きを同一の霊が行なうのであり,その欲するとおりに各々に分配するのです。」(コリント第一 12:10-11)
聖霊の人格性④ 聖霊には人格的な役割がある
聖霊は真理を教える
「しかし,その者,すなわち真理の霊が到来するとき,あなた方を真理の全体へと案内するでしょう。彼は自分の衝動で話すのではなく,すべて自分が聞く事柄を話し,来たらんとする事柄をあなた方に告げ知らせるからです。」(ヨハネ 16:13)
「わたしたちはそれらの事も,人間の知恵に教えられた言葉ではなく,霊に教えられた[言葉]で話します。わたしたちは霊的な[こと]に霊的な[言葉]を結び合わせるのです。」(コリント第一 2:13)
「というのは,聖霊とわたしたちとは,次の必要な事柄のほかは,あなた方にそのうえ何の重荷も加えないことがよいと考えたからです。」(使徒 15:28)
聖霊は証言する
「わたしが父のもとからあなた方に遣わす助け手,すなわち父から出る真理の霊が到来するとき,その者がわたしについて証しするでしょう。」(ヨハネ 15:26)
「そして,わたしたちはこれらの事の証人であり,聖霊もまたそうです。神はそれを,支配者としてのご自分に従う者たちにお与えになりました」(使徒 5:32)
「私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。」(使徒 5:32、新改訳)
もしも聖霊が非人格的存在なのであれば、使徒たちと共に「証人」として立つことができないでしょう。
聖霊は導く
「そこで霊がフィリポに言った,『近づいて,この兵車と一緒になりなさい』」(使徒 8:29)
「また,彼らはフリギアとガラテア地方を回った。アジア[地区]でみ言葉を語ることを聖霊によって禁じられたからである。」(使徒 16:6)
「神の霊に導かれる者はみな神の子であるからです。」(ローマ8:14)
聖霊は執りなしをする
「26 同じように,霊もまたわたしたちの弱さのために助けに加わります。[祈る]べきときに何を祈り求めればよいのかをわたしたちは知りませんが,霊そのものがことばとならないうめきと共にわたしたちのために願い出てくれるからです。27 それでも,心を探る方は,霊の意味するところが何かを知っておられます。それは神にしたがいつつ聖なる者たちのために願い出ているからです。」(ローマ 8:26-27)
「聖霊が執り成しをする」という事実は、聖霊の人格性を理解する上でとても大切です。まず、非人格的な存在が、一体どうやって「執り成し」をするのでしょうか?執り成しとは、誰かのために祈りを持って父なる神に願い出ることだからです。
また、もしも聖霊が父なる神の「活動力」なのであれば、その執り成しの主体は「父なる神ご自身」になってしまうので、父が父に向って執り成していることになり、意味不明な状態になってしまいます。父なる神は常に執り成しの祈りを受ける側の役割であり、執り成しの役割は、み子イエスと聖霊に与えられている、というのが聖書の教えです。
聖霊は冒涜され欺かれる
「このようなわけであなた方に言いますが,人はあらゆる種類の罪や冒とくを許されますが,霊に対する冒とくは許されません。」(マタイ 12:31)
「しかしペテロは言った,「アナニアよ,なぜサタンはあなたを厚顔にならせて,聖霊に対して虚偽の振る舞いをさせ,畑の代価の幾らかをひそかに取っておくようなことをさせたのですか。」(使徒 5:3)
もしも聖霊に人格的性質が無いのであれば、聖霊が欺かれる、という表現は不自然になります。
悪の三位一体からの考察
黙示録13章以降を読むと、キリストの再臨前の最終局面において、サタンが本物の三位一体を真似て、悪の三位一体を出現させることが預言されています。この点についての詳細は、既にYouTubeの動画「三位一体③ エホバの証人の反論に答える」にて話しています。
「そして,龍は自分の力と座と大きな権威を[その野獣]に与えた。 3 そしてわたしは,その頭の一つがほふられて死んだかのようになっているのを見た。しかし,その致命的な打ち傷はいえた。それで,全地は感服してその野獣に従った。 4 そして彼らは,野獣に権威を与えたことで龍を崇拝し,また,「だれがこの野獣に等しいだろうか。いったいだれがこれと戦いうるだろうか」と言って野獣を崇拝した。」啓示13:2~4
「また,わたしは別の野獣が地から上って行くのを見た。それには子羊のような二本の角があった。それは龍のように話しはじめた。 12 そして,第一の野獣のすべての権威をその前で行使する。また,地とそこに住む者たちに,致命的な打ち傷のいえた第一の野獣を崇拝させる。 13 また,大いなるしるしを行なって,人類の前で火を天から地に下らせることさえする。」啓示13:11~13
龍はサタンを表し、父なる神のコピーです。龍から権威を与えられる野獣は全世界から崇拝される一人の独裁者を表し、キリストのコピーです。そして、もう一匹の別の野獣は、獣の権威の全てを行使する一人の偽預言者を表し、聖霊のコピーです。この悪の三位一体が、本物の三位一体の構図と役割を、敵の側で見事に描いているのが興味深い点ですが、登場する偽預言者は、龍の「活動力・汚れた力」ではなく、人格的存在である偽預言者として登場します。
もしも、聖霊が「聖なる力」なのであれば、サタンの側も神の真似事として、偽預言者ではなく「汚れた力」を登場させるのではないでしょうか?聖霊の人格性を間接的に示唆するものとしては、興味深い事例だと思います。
また、聖書の中には聖書の働きに対をなすものとして、たくさんの人格的存在の悪霊の働きが出てきます。敵の側は常に人格的存在でものみの塔もそれを肯定しているのに、神の側の霊にだけはその人格性を否定する、というのは、奇妙な点です。
終わりに
このように、聖霊は父なる神とみ子イエスと同列に置かれている存在であること、「知性・感情・意志」等のあらゆる人格的な特徴が聖書全体に渡って多様に描かれており、真理を教え、導き、証しし、執りなる等の役割があります。
エホバの証人が教える通り、これらの全てを「擬人法」だと片づけることが本当にできるでしょうか?心を開いて、聖霊の導きを求め、聖霊の真の姿への理解を神の求めるのなら、神は必ずその真理を悟らせて下さるでしょう。
次の記事では、聖霊の人格性を否定するエホバの証人の主張を一つ一つ取り上げ、その主張に答えていきたいと思います。